●「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について
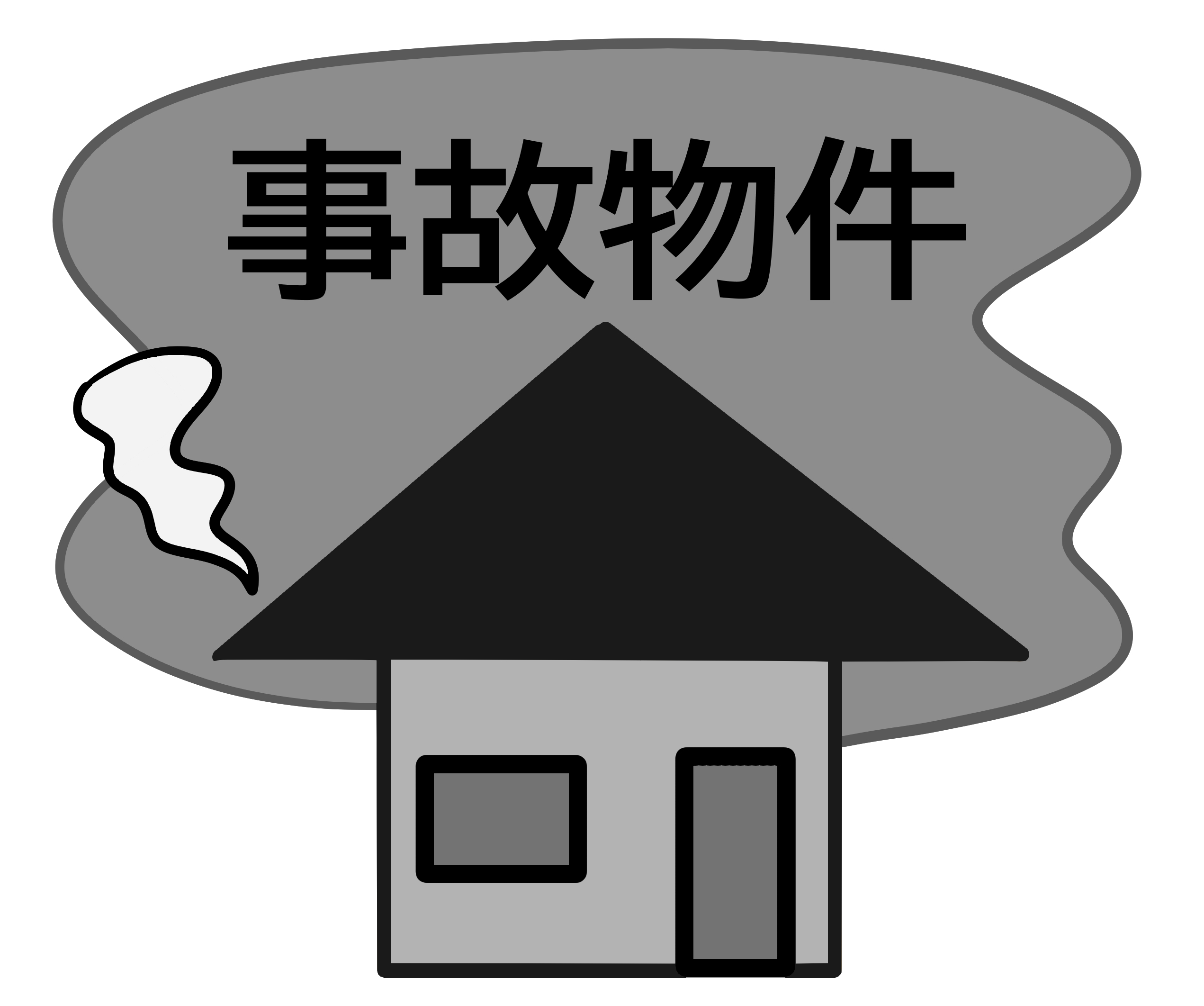
〇「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が令和3年10月8日に国土交通省が発表しました。
それまでは、賃貸・売買物件も含め部屋の中で入居者が亡くなった場合、自然死なのか自殺なのか、事件で亡くなったのかなどの理由や告知しなくてはならない期間などの基準が、過去の判例や個々の業者の判断にゆだねられて明確な基準がなかったため、トラブルに発展する場合もあったため、判断基準とするガイドラインを国土交通省が不動産取引の活性化を図る目的で取り纏めたものです。
1.ガイドライン適用の不動産の範囲:住宅として用いられる不動産=居住用不動産における人の死を対象
2.調査の対象・方法:宅地建物取引業者は、売主・貸主に対し、告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。告知書等により、告知が無い場合でも人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは、売主・買主に確認する必要がある。
3.一般的な基準(告知しなくても良い場合):
①【賃貸借・売買取引】対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥(ごえん)など。※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死
※事案発生からの経過期間の定めなし
・②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知する必要がある。
・告知しなくても良いとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知する必要がある。
・人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告知する必要がある。
・告知する場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告知する。
・亡くなった方やその家族の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、故人や家族のプライバシーや具体的な死の態様などを告知する必要はない。
・取引に当たって、宅地建物取引業者はトラブルの未然防止の観点から、買主・借主の意向を事前に十分把握し慎重に対応することが望ましい。
以上、高齢者の一人暮らしが増えている中で、ガイドラインが発表され、これを基に不動産の取引がスムーズにトラブルなく行われることを願います。
◎「訳アリ物件」や不動産売却のご相談はA-ハウスへお任せください。
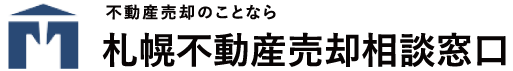
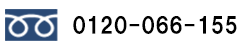

 0120-066-155
0120-066-155

