●契約不適合責任とは

〇民法改正後の契約不適合責任:2020年4月に民法が改正され、それまでの「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」となりました。
・買主の請求できる権利
1.履行の追完請求権(改正後追加):修復可能な欠陥や対策することで性能回復が見込まれる場合に請求可。売主が知らなくても請求可能。
2.代金の減額請求権(改正後追加):一定の期間を設けて目的物の補修などを求めたにもかかわらず売主が対応しない場合に請求可。「事故物件」などの心理的瑕疵や修復不可能な場合や売主が請求に応じる意思がない場合は追完請求なしで減額請求も可。
3.契約解除権:一定期間に催告しても、履行がされない場合は契約解除が可。ただし、契約内容に適合しない部分が軽微な場合は不可。契約が解除されると、契約前の状態に戻す義務が発生し、売主は受け取った売買代金を返還しなければなりません。
4.損害賠償請求権:売主に故意や過失がない欠陥については、損害賠償請求は不可。
〇契約不適合責任で売主が注意するポイント
・契約不適合責任の通知期間を具体的に設定:一般的な個人の場合は引渡しから3カ月以内に設定する場合が多い。
・物理的瑕疵を把握する:不具合などを書面に残し買主に伝えるようにする。
・瑕疵保険に加入する:中古住宅の場合は「既存住宅瑕疵保険」があります。事前に有資格者の建築士が状況調査を行い審査が通ると保険に加入できる。保険期間は1~5年、保険の対象は「構造体力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」が基本で、さらに「給排水管路」や「電気設備」などのオプションを付けることが可能。
ただし、時間と調査費用や保険料などのコストが発生するのと、建物が新耐震基準かどうか、傾きが無いかなどの要件もあるので一考が必要と思われます。
〇築年数が経過している場合や不具合の箇所が多いなどの場合、価格面で調整し、売主の「契約不適合責任を免責」にする場合があります。
契約不適合責任は、最終的に売主が買主に負う責任ですが、仲介業者が介在する場合はその仲介業者のスキルも必須となりますので、経験豊かで売主のリスクを軽減することができる「信頼できる業者選び」が大きなポイントとなります。
不動産取引における契約不適合責任の範囲は広く、責任が生じた場合の負担は大きいので、不動産の売却の方向性や売却価格の設定から成約に持っていく戦略をうまく立てられる業者に依頼できるかどうかが最大の重要なポイントといえます。
◎契約不適合責任のことや不動産売却のご相談はA-ハウスへお任せください。
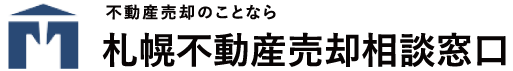
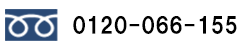

 0120-066-155
0120-066-155
